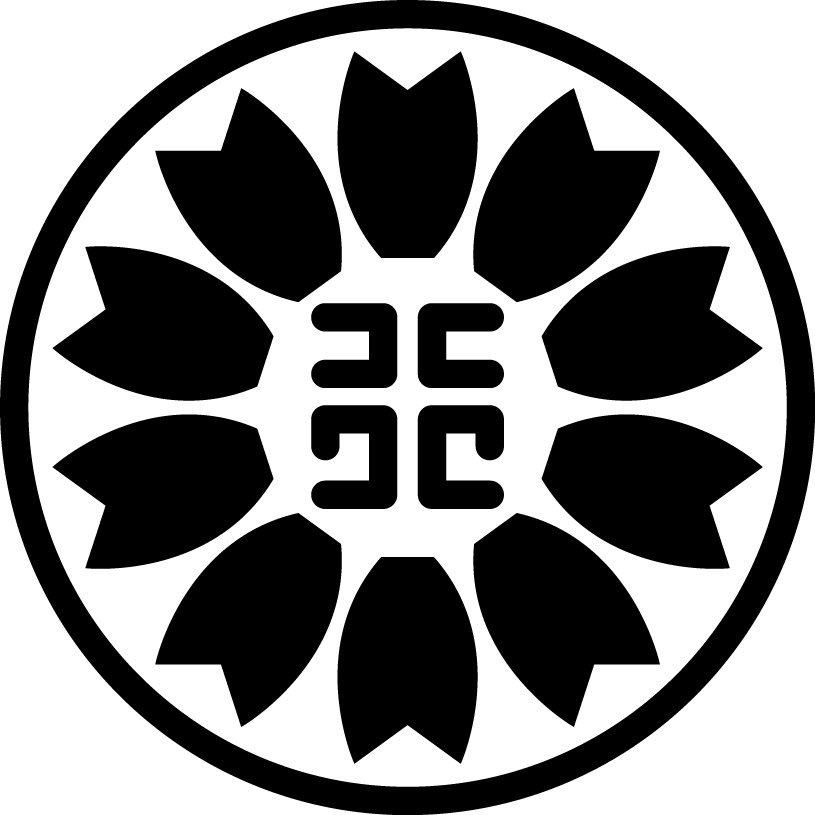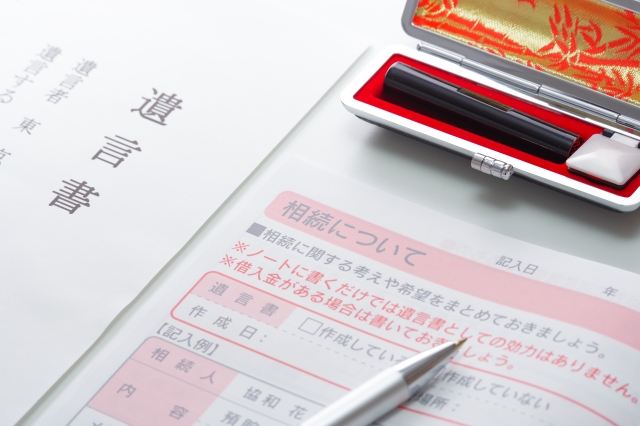相続手続き 遺言執行業務 (遺言があるケース)
遺言書の探索
相続が開始されたときに最初に行うのが被相続人の遺言書の探索です。
被相続人(遺言者)がご家族や周囲の方(行政書士などの法律専門家)に遺言を作成保管されている事実を告げられていれば、遺言書の探索は必要ありません。
しかし、遺言書の存在有無が不明な場合は、念のために遺言書を探索することになります。というのも、遺産分割の途中や成立後に遺言書が発見されるケースもあるからで、その場合相続人全員が合意した協議が成立すればまだしも、相続人の中の一人が合意に賛成しなかった場合は協議がストップし、紛争状態になることもないとは言えないからです。
遺言執行業務の具体的流れ
(注)以下は遺言書の検認が必要ないケースで説明しています。自筆証書遺言でも法務局保険制度を活用されている遺言書は検認手続きが不要です。
(1)遺言執行人の就職
遺言書で遺言執行者が指定されていれば、遺言執行者が遺言の内容を実現する目的で相続財産の管理その他遺言執行に必要な一切の行為をするすべての権利と義務を有します。(民法1012条2項)
遺言執行者は直ちに遺言内容を相続人に通知しなければなりません。また遅滞なく財産目録を作成し、相続人に交付しなければならないとされています。
遺言執行者の職務が法範囲に及ぶため、第三者(例えば行政書士などの法律専門家)にその任務を行わせることができるとされています。
(2)遺言の内容確認
遺言書の内容を相続人全員が確認します。遺産分割は基本的に遺言書にそって相続手続きを勧めます。
ただし、相続人の全員が遺言書と異なる遺産分割協議を行い包囲することは可能です。
また、遺言で法定相続分と違う割合で相続人の相続させることや、相続人ではないものに遺贈することも可能ですが、兄弟姉妹以外の法定相続人(およびその代襲者)には遺留分という最低限相続できる権利が認められています。
(3)相続人の調査
遺言の通りに相続手続きを進める場合でも、先に述べた遺留分等の権利を確認するために、相続人の確定を目的とした相続人調査は行った方がよいでしょう。
(4)相続財産の調査
同じく遺言書に沿った手続きを進める場合でも、記載が漏れている財産について調査を行い、必要な手続きを進めるべきでしょう。
特に、不動産については山林や田畑などすべてが遺言書に網羅されていないケースもあります。遺言書を確認し、相続財産に漏れがないか確認しましょう。
(5)遺言の執行
遺言内容を実現するために、不動産は司法書士に相続登記手続きを、金融機関の預貯金は解約若しくは名義変更を行います。
その他財産の相続手続きを実行します。
必要な場合は、税理士が相続税申告を行います。
(6)遺言執行の完了
遺言執行者は相続人・受遺者に「遺言執行事務完了書ならびに顛末報告書」を提出し業務を終了します。