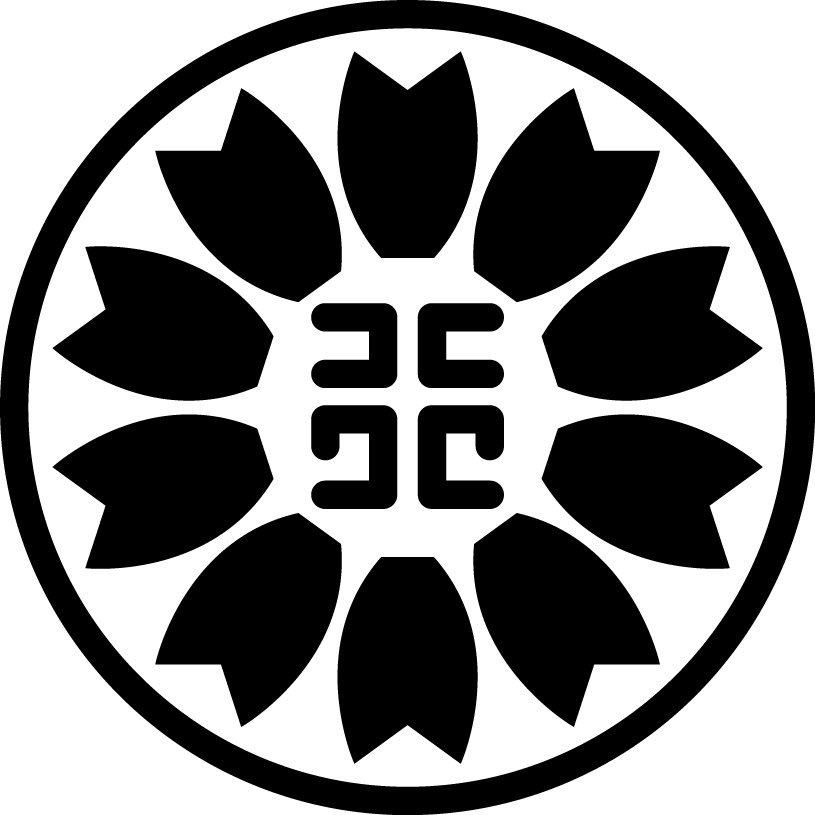遺言書の作成
遺言書を作成するメリット
①あなたの希望する方に希望する財産を残すことができます。
ご自身の望み通りに財産を相続させたい場合は、財産の目録を作り、それぞれの財産をどなたに相続させるかを遺言書に書き残しておけば、原則はご自身の意思通りの相続を実現させることができます。
「長年生活を共にしてきた配偶者○○に財産の全部を相続させたい」
「(推定)相続人ではないが、長年お世話になった○○○に財産の一部を残したい」
「自分の会社の事業継承は○○○のようにしたい」
「私の家族ともいえるペットの○○の世話をすることを条件に、○○の財産を子ども○○に相続させる」
(注)遺言の内容はご相談のうえ、相続人の遺留分も考慮いただきながら、あなたのご意思を反映できる最善の内容をご一緒に考えさせていただきます。
②遺産分割協議(相続人全員による話し合い)を経ずに、財産の分割が可能となります。
遺言書がない場合、基本的に相続人全員が遺産相続について協議を行い、相続人全員の合意を経ないと遺産の分割ができません。相続人の一人でも協議している内容に反対すると、手続がストップします。また、お一人でも音信不通の相続人がいらっしゃると、協議自体がスタートできません。そうなると遺産に含まれる預貯金にも手が付けられないということになります。
しかし有効な遺言書があれば、その内容に沿って、相続人のきょぷぎと合意を必要とせずに、相続を進めることができます。不動産の名義変更も可能ですし、預貯金の解約や名義変更ももちろん進めることができます。
遺言書で「遺言執行人」が指定されていれば、これら遺言書の内容に沿った相続の手続は、遺言執行人一人でスムースに進めることが可能です。
具体的な流れ
(1)初回面談
直接お会いする方法、あるいはzoom他インターネット会議などリモートの方法で初回1-2時間程度、面談をお願いします。
(2)作成スケジュールと概算見積書の提示
面談でお話を伺い、遺言の方式について検討・決定後に、全体の作業手順と大まかなスケジュール、概算見積書を提示させていただきます。
(3)委任契約書の締結
スケジュールと見積もりを確認いただき、依頼者に合意いただければ、業務内容を明記した委任契約書を締結させていただきます。
(4)必要書類の準備
遺言書の要式により異なりますが、依頼者にご用意いただく書類がある場合は準備をお願いします。
そのほかの必要書類はこちらで準備します。
(5)相続関係説明図の作成
相続人を確定するために収集した戸籍等から「相続関係説明図」を作成します。必要に応じて推定相続人の調査も行います。
(6)財産目録の作成
遺言書に記載する「財産目録」を作成します。財産を特定するための書類の写しでもOKです。
(7)遺言書の文案作成
具体的な遺言書は遺言の様式やその保管方法によって異なります。別途ご相談ください。
自筆証書遺言でも自宅等ではなく、法務局に保管する制度もあります。公証役場で公証人に遺言書の内容まで確認してもらう方法もあります。
(8)アフターフォロー
遺言書の内容はいつでも変更することが可能です。変更のお手続きも行いますので、相談ください。
<初回面談の内容イメージ>
A)説明させていただく事項
①法律で定められている相続の基本原則。遺言は自由にすることができる(民法961条、963条など)のですが、いくつかの制限もついています。
②遺言の要式。遺言はその要式が民法に定められています。要式に従わない遺言書は無効となります。
③遺言書の検認の要不要。遺言書に沿った相続手続の中で「家庭裁判所の検認」が必要な場合について説明します。
④その他必要と思われる法的な事項について説明します。
B)お話しいただきたい事項
①遺言を残そうと思われたお考え・お気持ち
②遺言者(依頼者)について
③(推定)相続人と受遺者について 「受遺者」とは法律で定められら「法定相続人」以外の最残を受け取られる予定の方
④相続の対象となる財産について
⑤遺産分割の方法について
⑥その他