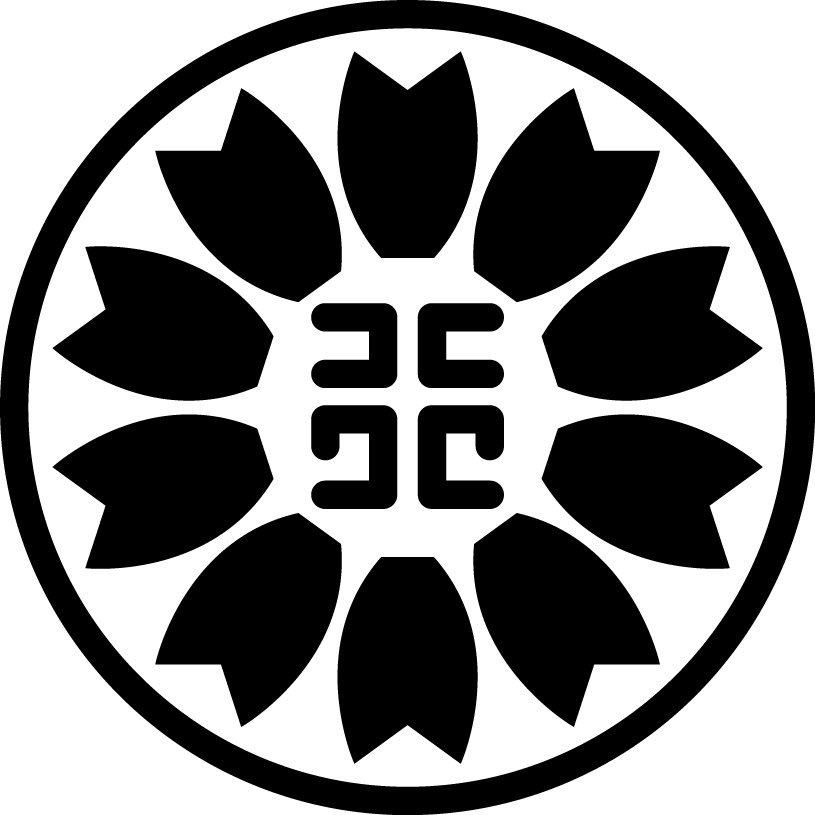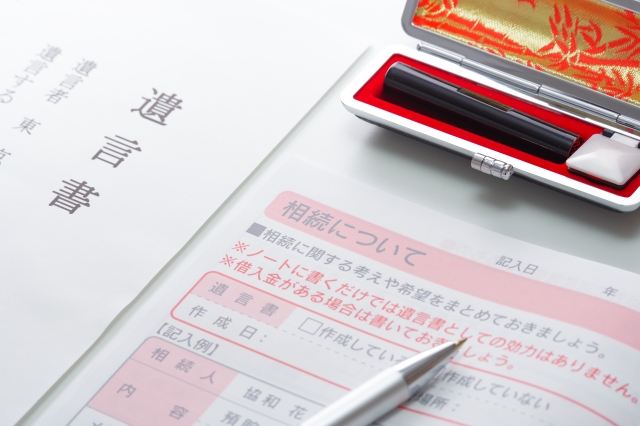相続手続き 組遺産分割協議 (遺言書がないケース)
遺産分割協議
遺言書がないケースでは、相続人全員で遺産分割協議を行い、相続人全員の合意をもとに「遺産分割協議書」という書類を作成し、全員の合意があったことを第三者に明らかにしたうえで、相続手続きを進めていきます。協議書に署名押印している相続人以外に相続人の抜け漏れがないことを公的な書類で明らかにしなければなりません。
また、相続する財産の内容も調査を行います。
相続税関連の相談に関しては税理士を、年金関係の相談には関しては社会保険労務士をご紹介します。
お気軽にご相談ください。
具体的な流れ
(1)初回面談
直接お会いする方法、あるいはzoom他インターネット会議などリモートの方法で初回1-2時間程度、面談をお願いします。
〇相続に関する基本的な原則をご説明します。
〇遺言書の有無についてお伺いします。
<<この先は遺言書がないケースです>>
〇被相続人と相続人についてお伺いします。
〇相続財産についてお伺いします。
〇現時点での協議の進捗についてお伺いします。
(2)作成スケジュールと概算見積書の提示
面談でお話を伺った相続人の構成(続柄と人数)及び財産の規模に応じて、全体の作業手順と大まかなスケジュール、概算見積書を提示させていただきます。
(3)委任契約書の締結
スケジュールと見積もりを確認いただき、依頼者に合意いただければ、業務内容を明記した委任契約書を締結させていただきます。
(4)必要書類の準備
相続手続きに必要な書類のうち、相続人にご用意いただく書類(印鑑証明等)を手配をお願いします。
そのほかの必要書類はこちらで準備します。
(5)相続関係説明図の作成
相続人を確定するために収集した戸籍等から「相続関係説明図」を作成します。必要なら法務局で「法定相続情報一覧図」を作成します。
(6)財産目録の作成
「財産目録」を作成します。
(7)調査報告及び遺産分割協議書の文案作成
相続人全員で協議を行っていただきます。相続人の皆さんのお考えが同じ方向に向いたところで遺産分割協議書の文案を作成します。
相続人全員の合意をいただけたら、文案を確定し、相続人全員の記名と(実印)押印をいただきます。
(8)相続財産の分割手続き
不動産は司法書士に相続登記手続きを、金融機関の預貯金は解約若しくは名義変更を行います。
その他財産の相続手続きをお粉います。
必要な場合は、税理士が相続税申告を行います。
(注意点)
遺産分割協議の中で、紛争状態になってしまった場合は、委任契約条項に基づき連携する弁護士に業務を引き継ぐことになります。
(行政書士法第1条の2第2項、弁護士法第72条)